ACP研修レポート|主任ケアマネが学ぶ「それは誰の意向?ぶれない意思決定支援」
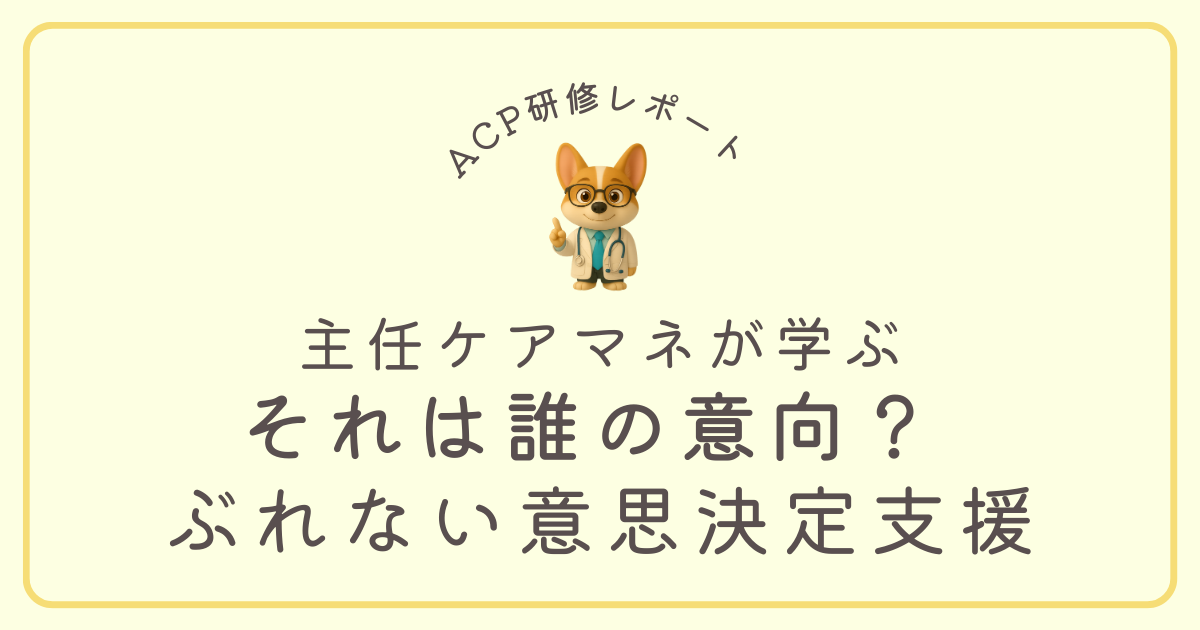
2025年7月25日、茨城県阿見町の地域包括支援センター主催で、主任ケアマネジャーを対象とした研修会「それは誰の意向ですか?ぶれない意思決定支援」を開催しました!
高齢者支援の現場では、本人の意思を尊重したいけれども、家族や医療ケアチームの意見に揺れてしまう‥という場面が少なくありません。特に本人がもう自分でお話ができない状態にあるとき、「この人は一体何を望んでいるんだろう」と悩む場面は毎日経験されているんではないでしょうか。
本研修では、症例ワークやグループ討論を通じて「ぶれない意思決定支援」に必要な視点を実践的に学びました。最も伝えたいことは‥
これを忘れると、意思決定支援がぶれていきます。
参加者からは「今までの自分の意思決定支援がなぜぶれていたか分かった」と、主催者としては嬉しい声をいただけました。本記事では、その研修の様子と伝えたいメッセージをお届けします。
📅 開催概要と背景
2025年7月25日、茨城県稲敷郡阿見町にて主任ケアマネジャーを対象としたACP研修会「それは誰の意向か?ぶれない意思決定とは」が開催されました。研修は主任ケアマネの更新研修として3時間にわたり、対面形式で実施され、地域の中堅層を中心とした約70名の主任ケアマネジャーが参加しました。(これだけ集まるのは珍しいとのこと‥ありがたいことです😊)
近年、ACP(Advance Care Planning:人生会議)の重要性は全国的に高まっています。しかし現場では、
本人がもう意思表示ができない状況や、家族や医療者の意見が交錯する中で「誰の意向を優先すべきか」という難題に直面する場面が少なくありません。とりわけ主任ケアマネジャーは、チーム全体の意思決定を支える立場にあり、その力量が地域ケアの質を左右すると言っても過言ではありません。
今回の研修会は、そうした現場の課題に真正面から向き合い、「ぶれない意思決定」を実現するための具体的な視点と手法を学ぶことを目的に企画されました。単なる知識の習得ではなく、実践的に活用できるスキルを身につけることを重視し、ワークを多めに取りいれました。
📝 研修の流れと参加者の様子
今回の研修は、参加者自身が主体的に考え、意見を交わすことを重視した実践型の構成としました。単なる講義ではなく、症例を題材にしたワークや討論を通じて、現場で直面する課題をリアルに体験できるプログラムでした。
- 症例ワーク:仮想事例を用い、4分割表を活用しながらグループごとに分析と意見交換を実施
- 推定的意思を全力で考えるワーク:本人が話せないとき「どのように本人の意向を推定するか」を整理する視点を学習
- 公開討論:全グループのオープンなディスカッションにより、「誰の意向を優先すべきか」という本質的な問いを深掘り
- :最後に自らの実務にどう活かすかを内省し、明日からの実践に直結する学びを整理
これら一連のワークを通じて、参加者は
もっとお話ができるうちに、本人にとって大切にしたい価値観を聞いておかないとダメなんだな‥
と、単なる知識のインプットではなく、ACPの重要性を“腹落ち”させる研修となりました。
💬 参加者の声
アンケートでは、満足度は非常に高く、ほとんどの参加者が「実践に役立つ」と回答しました。特に次のような意見が目立ちました。
- 実践に役立つ
「意思を推定するための根拠を明確にして、多職種と話し合っていきたい。」
「何気ない会話の中で、本人の価値観を探っていくことの大切さを学んだ」
- 思考が整理できた
「4分割表で情報を整理することで、思考が整理できた」
「本人なら何と言うか、どのように判断するのかを判断軸にして議論する大切さを学んだ」
- 専門職としての責任感
「自分がこれまでどれだけ本人の意向を考えられずに物事を決定していたかを痛感した。」
「本人の意思を全力で推定していこうと思う」
✅ まとめ
今回のACP研修会では、主任ケアマネジャーが直面する「誰の意向を尊重すべきか」という難題に対して、具体的なケースを通じて考え抜く機会となりました。すべてのワークを通して改めて「ACPは現場を支える基盤である」という理解が深まり、参加者からも高い満足度が寄せられました。
今後も、地域に根ざした多職種向け研修を継続的に開催していく予定です。次回の開催情報や研修資料の案内は、以下の公式媒体で発信しています。
- 📲 LINE公式アカウント:最新情報・資料ダウンロードはこちら
- ▶️ YouTube「Dr.たろの在宅・緩和ケアch」:過去の研修ダイジェストを公開中
👉 LINEで最新情報を受け取る
👉 YouTubeで動画を見る
また、自治体や地域包括支援センター、専門職団体などからの研修会依頼も受け付けています。対象やテーマに合わせたカスタマイズ研修も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
地域の実践を支える研修に、ぜひご参加ください。
